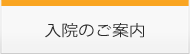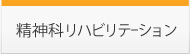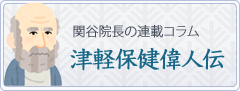津軽保健偉人伝 第3回
書物に描かれた藤代健生病院
関谷 修
何気なくページをめくっていると、唐突に当院の名前を見出すことがあります。その数は決して多くはありませんが、その度に、この上ない光栄を感じました。開設者の津川武一先生を筆頭に、当院に所縁の深い医師らの大きな活躍があったからこその栄誉です。同時に、記されるに相応しい内実を当院は有しているという密かな自負もありました。
以下に、その数冊を紹介させていただきます。
風祭元『精神科医の雑学読書』あき書房(2007年) 118頁
津川武一先生も明治43年生まれ、弘前高校出身で、昭和14年に東京帝国大学医学部を卒業して精神科に入局し、戦後、弘前市に精神科の津川診療所、藤代健生病院を設立し、また、青森2区選出の共産党の衆議院議員としても活躍した方である。
東京大学医学部出身で元帝京大学教授の風祭先生が、精神医学、精神科医療に関連する書物13冊を選び、一冊ずつに内容を紹介し、自らの読後感を綴ったものです。
その中の一冊として、風祭先生は石上玄一郎著『精神病学教室』を取り上げ、冒頭から次のように絶賛されています。
「私はこの本を読んで、記述の正確さに驚嘆した。小説の中で精神科病院の入院患者の日常を描いた作品は少なくないが、大学病院の精神科病室の情景、医師の働きぶり、研究室や医局の風景、教授のポリクリ診察、病理解剖の様子などがこれほど生き生きと書かれている小説はない」
さらに、本論の最後では文学史上で本作の持つ意義についても触れています。
「この小説は、戦時中の昭和文学史を語るには必ず題名が出てくる作品であるが、60年以上前に発表されたもので、現在では入手が難しい。評論家の奥野健男は、この小説が、後の遠藤周作「海と毒薬」、北杜夫の「夜と霧の隅で」。加賀乙彦の「フランドルの冬」などの医学を題材としたすぐれた作品につながるものと論じている。」
これほどの、手放しの賞賛ですが、では、なぜ、この文脈で当院の名が出てくるのでしょう。本論の後半で、小説完成までの裏事情が語られます。
もとはと言えば、昭和16年ごろに津川武一先生が既に同じタイトルの小説を書いていました。 医学が時事刻々と進歩する一方で、その影で犠牲とならざるを得ない患者さんが存在するという深い葛藤を軸に据えた作品でした。
津川先生は、完成した原稿を真っ先に先輩医師の高橋角次郎先生に見せます。高橋先生は一読した後、「筋立てとしては面白いが、文章が下手だな」と辛辣な感想をもらしました。津川先生は、落胆したかも知れません。逆に、発奮したのかも知れません。津川先生からこの経緯を聞かされた弘前高校時代の同級生・石上氏は、津川先生の着想を活かしつつ、大幅な表現の変更を行い、本作を完成させたのです。
原案は津川、執筆は石上という弘高の両雄が放った快作です。戦中期に刊行された本作品と、昭和50年代に開設された当院は、大戦を挟み大きな時間的隔たりがあります。でも、ひとえに津川先生の功績のおかげで当院の名が風祭先生のご著書に記されることとなったのです。
鈴木晃仁、「精神疾患の声の歴史 ー 近代日本の精神科臨床と文学」 50頁
『シリーズ精神医学の哲学 2 精神医学の歴史と人類学』(2016年)所収 東京大学出版会
石上にこの作品を書かしめたのは、当時東大の精神科で副手の職にあった津川武一との交流であった。(中略) 小説内で描かれている医療行為と研究は、実際に津川が行なっていたものであり、その専門的な内容が非常に技術的に正確に描かれているため、当時の教授の内村祐之は、この作品を津川が書いたものと誤解して、怒って津川を破門したといううわさが立った。
これは、番外です。なぜならば、当院の名は一切出てきません。津川武一先生の名が記されているだけです。でも、本書の出版は2016年9月。津川先生が没して30年の時間が過ぎているのに、今も新たにページに名を刻まれる栄誉と幸運に驚きを禁じ得ません。
急速な近代化を遂げた日本の、その片隅で精一杯の生を送った精神疾患に苦しむ人々を描いた文学作品が実は極めて価値の高いものであると、本書は指摘をします。
風祭先生が優れた文学作品であるとして取り上げた『精神病学教室』が、本論文では、戦前の貧しい精神科医療の中で黙殺されがちな患者らの「声なき声」の希少な証拠として、さらには日本文学の一角を占める「狂気」の視点を措定した代表作として、その名が挙げられています。
安彦良和『革命とサブカル』言視社(2018年) 274頁
今、藤代健生病院の院長をしている関谷医師が、津川武一の病跡学をやっていて、病院の記念誌に書いています。
まったくの手前味噌で、汗顔の至りです。機動戦士ガンダムの生みの親、安彦氏がかつて弘前大学で学生運動に熱中した仲間たちと対談する中で、当院の元・院長でいらした蟻塚亮二先生が登場します。そして、上の言葉を語るのです。
本文では、蟻塚先生の学生時代での政治活動や、津川武一先生との関係など、あまり拝聴する機会のなかった事実も明かされ、とても興味深い内容となっています。
さて、蟻塚先生に取り上げていただいた「津川先生の病跡学」ですが、この文章は現在、藤代健生病院のホームページで閲覧できます。ただし、『津川武一日記』を紹介する前文という位置付けにあるため、病跡学的論考と呼ぶにはかなり物足りない文章であることは、あらかじめお断り申し上げます。過度な期待は持たれずに、ホームページ(津軽保健偉人伝 第2回『津川武一日記』に読む藤代健生病院開設までの軌跡)をご覧ください。
岡田靖雄 『吹き来る風に』中山書店(2011年) 257頁
関連として、さらにいくつかあげておこう。
日本の精神科医療の歴史と課題』藤代健生病院、1986年 これは同院開設10周年記念行事の一つとして、1986年に行なった講演の記録である。
1986年、当院は開設10周年を迎えました。当時の院長、蟻塚亮二先生が記念講演を岡田靖雄先生にお願いしたところ快諾いただき、実現したものです。現在、開設44年になるので、はるか以前のことになります。語り手も聞き手も双方が熱気にあふれた講演の様子は、当院10周年記念誌に余すところなく掲載されています。講演の前半は戦前に使われていた拘束具、水治療の光景など、貴重な映像が150枚に及ぶスライドで提示され、本邦での精神医療の黎明から現代までの軌跡が語られました。今では、それらの画像の全てが先生のご著書『日本精神科医療史』に掲載されています。後半は、歴史的な視点から日本の精神科医療の課題を次々に明示して行くというものでした。その時の記憶を岡田先生がしっかりと持ち続けていたことに驚かされました。
講演の冒頭、「精神科の医療史ということで話しをきいてくださろうと声をかけてくださったのは、蟻塚先生がはじめてでありまして、そういった意味で、本日は嬉しさと不安とをもってお話しします」と岡田先生は語り始めます。講演の最後では「歴史を通してみてきますと、精神科医療を取り巻く矛盾の根は非常に深い、ということです。地球の底まで届くぐらいに深いんです」と、予定の時間をはるかに越えて、なお、念を押すかのように聴衆に語り掛けています。
2016年には当院開設40周年を迎え、記念誌を発行しました。岡田先生には同誌にもご寄稿いただきましたが、30年経っても主張する内容は全く揺らぐことがなく一貫していたことは言うまでもありません。
野中猛『心の病 回復への道』岩波書店(2012年) 38頁から47頁の抜粋
私が勤務した精神病院の初期研修は変わっていた。というより本当に必要な研修を工夫していました。最初は閉鎖病棟の患者として病室に入院しました。先輩の患者さんがいろいろ教えてくれます。薬を舌の下に隠して飲んだふりをする技術、幻聴は消えたと言えば退院できること、どの看護者がいじわるか、などです。
次に掃除のおばさんたちの集団に入れられます。窓や扉の構造や、建物の壊れた部分に目がいきます。患者さんは看護師に相談できないことを掃除のスタッフに相談します。
そのあとにメディカルスタッフのそれぞれのグループで研修を受けます。
そしてようやく病棟に配属されました。上級医ー下級医という指導体制が形成されますが、実務的な医療活動はみんな看護者から学びます。
私はメディカルスタッフに頭が上がりません。医師にはできない事柄が、いっぱいあることを実感しています。
私が精神科研修をした津軽にあるこの病院は、中堅から若手の精神科医が集まって、古い精神病院を改革し、理想の精神医療を実践しようと意気に燃えた、ちょうどその時期にありました。改築前の古い木造の精神病院は、特有の臭いがこもり、床だけがギシギシ鳴る、不気味なほど静かな空間でした。何百人もの人がいるはずなのに、衣ずれの音もおしゃべりの声も聞こえないのです。
新病院建設計画が動き出し、新しい土地にすべてを立て直しました。欧米の最新状況を見学して工夫した構造です。津軽の長い冬を想定した広いデイルーム、ほとんどが一階建て、まわりはリンゴ畑、岩木川もすぐそばです。ここに閉鎖の急性期病棟ひとつと、開放病棟三つ設け、そのうちのひとつは北東北で最初のアルコール症専門病棟でした。この精神病院の親病院となる総合病院にも精神科病棟を設けて、神経症やうつ病を対象としました。
津軽一円の人々の健康を守るという方針で活動していましたから、病院にこもる考え方はありません。地域住民の夜の集まりに顔を出し、往診や訪問を日常的に行っていました。予防活動から就労支援まで、すべてを精神病院が手がけていました。
本文中に「藤代」の名は一切出て来ませんが、紛れもなくかつての藤代健生病院での出来事です。同時に、ここに記されたのは、昭和40年後半から50年前半にかけての一民間病院の実態に関する貴重な資料でもあります。「変わった研修」と題された文面から伝わるのは、今なら研修医放置と言われかねないプログラム不在のあり様と、しかし、だからこそ実りの多い経験となったという逆説的な教訓です。
指導医師はいても、その指導は最小限。その代わりに、医師以外の全ての職員が研修医の指導を引き受けていた。そこから20年経った時期に私は研修医として過ごしましたが、その時もなお「看護が医者を育てるのが藤代流だ」と言う言葉を何度か耳にしました。今となっては懐かしい思い出ですが、開設当初の意気込みが深く職員の意識に浸透していたのでしょう。そして、今もその意識が藤代健生病院全体に脈々と受け継がれていることを私は密かに感じています。
<おわりに>
地方の一精神科病院が、書籍の中で取り上げられるということは決して多くあることではありません。その栄誉は身に余るものです。ただ、本稿は当院の栄光の歴史を書き並べることを目的としたわけではありません。生活協同組合という当院のあり方、戦前の無産者医療に始まり藤代開設まで漕ぎ着けた長い長い道のり、そして所縁ある多くの人々、これらの際立つ個性を持つ藤代健生病院の姿は、客観的な場所に立つ人々から見ると、果たしてどのように映るのであろうか、という観点を含ませながら、この一文を綴りました。
他者の視点と言葉を通じて、私たちの組織を見つめ直しつつ、さらに当院自体が時代の影響を色濃く受けながらも比類なき個性を打ち出し続けて来たという証しをここに刻み、次なる世代にしかと伝え、記録を残して行くこと、それが私の意図であり、願いでもあるのです。
以上
掲載:2020年9月14日
Copyright © 津軽保健生活協同組合 藤代健生病院 All Rights Reserved.