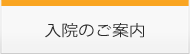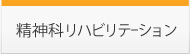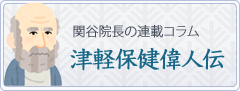津軽保健偉人伝 第2回 津川武一
『津川武一日記』に読む藤代健生病院開設までの軌跡
藤代健生病院 関谷 修
<解題>
早いもので、私が藤代健生病院に勤務して四半世紀が過ぎようとしています。この間、私の中でいくつかの疑問が静かにうごめいていました。果たして藤代健生病院開設にあたり、当時の津軽保健生活協同組合長であった津川武一先生はどのような構想、理念、願いを持っていたのだろうか。精神科医師として先生は新病院にどのような期待を抱いていたのだろうか。そして、当院開設当時の熱気や志向性、職員集団の文化が、今もなお、脈々と私たちの日頃の仕事振りに連なっているのではなかろうか。
そのようなことを知りたくて、今回、『津川武一日記』全十巻を紐解いてみました。
意外にも『日記』の中に藤代健生病院に関する記述は多くはありません。勿論、経営責任者として建築費用の金策に奔走した記載はありました。また、建設業者や地域との折衝の場面も描かれていました。ですが、新たな精神科病院で新たな精神医療に取り組む熱意を読み取るには、とても心もとない文章量でした。
 確かに、大清水健生病院を藤代の地へ移すという意味からすれば、組織としては連続したものですし、多少ベッド数と職員数が増えたところで患者も職員も同じ顔触れではあるでしょう。何より、当時、先生は衆議院議員の職にあり、己の一病院よりも国政での活躍に力点が置かれていたのでしょう。新病院の設計や医療の内容まで先生が口を挟む余裕はなかったのかもしれません。
確かに、大清水健生病院を藤代の地へ移すという意味からすれば、組織としては連続したものですし、多少ベッド数と職員数が増えたところで患者も職員も同じ顔触れではあるでしょう。何より、当時、先生は衆議院議員の職にあり、己の一病院よりも国政での活躍に力点が置かれていたのでしょう。新病院の設計や医療の内容まで先生が口を挟む余裕はなかったのかもしれません。
でも、たとえ藤代健生病院に関する記載は多くなくとも、周辺の事情を通じて開設までの曲折に富む経過を知ることの意義は少なくないと考えます。加えて、藤代開設までの時期が、40歳代から60歳代という先生自身の壮年期に当たります。私は、この巡り合わせに只ならぬ縁を感じます。
なので、本論では大清水健生病院から藤代健生病院への軌跡に関する内容を縦軸として、そして先生の足跡を横軸として織り成すことで文脈に奥行きを与えることにしました。
先生の生涯は、なにしろ振れ幅の大きいものでした。貧農の出身ながら東京帝国大学医学部に入学。放校処分とその後の復学。日本共産党からも除名処分を受けながらも、その後に復党。二回の受刑体験の一方で、国会議員としての勇躍。青年軍医としての戦争体験と、その後の平和活動への傾注。私生活では二回の結婚と、愛娘の夭逝など、語る材料には事欠きません。これらの起伏の中から、本論では主に以下の三点を横軸として配置しました。
転向と破門
いささか中世的な色合いを帯びた項目ですが、この二つは先生の全生涯に渡る「陰のモチーフ」と言えるほどに大きな意味を持っています。
物心ついた頃から武一少年の目に映るものは貧しさと過酷さばかりでした。毎秋になると米俵を山積みにした大八車を父と一緒に引きながら地主の家に出向き、年貢を納めます。普段は柔和な父の顔からこの時ばかりは笑みが消えることに武一少年は気付いていました。少年の心に刻まれた社会的矛盾の一場面が東京で知った社会主義思想と結び付いた時を境に、武一青年は政治活動へと猛然と進んで行きます。しかし、治安維持法という巨大な網が張り巡らされた時代でした。武一青年は逮捕され、監獄へ送られます。そして、遂には転向を表明します。大学合格まで挫折を味わうことのなかった青年にとっては、初めての、そして余りに過酷な体験でした。
 その後、武一青年は復学を果たし、卒後には精神科の道に進みます。かなりの遠回りではあったものの、一旦、踏み外しかけた軌道へと無事に戻れました。ところが、またしても鬼門が待ち受けていたのです。先生の友人が文学誌に発表した医学小説の筋立てが大学教授の逆鱗に触れ、濡れ衣を着せられた先生は大学から追放されてしまうのです。研究論文をいくつも書き上げ、まだまだ医師としての修行中の身であった武一青年にとって、二度目の大き過ぎる挫折体験でした。
その後、武一青年は復学を果たし、卒後には精神科の道に進みます。かなりの遠回りではあったものの、一旦、踏み外しかけた軌道へと無事に戻れました。ところが、またしても鬼門が待ち受けていたのです。先生の友人が文学誌に発表した医学小説の筋立てが大学教授の逆鱗に触れ、濡れ衣を着せられた先生は大学から追放されてしまうのです。研究論文をいくつも書き上げ、まだまだ医師としての修行中の身であった武一青年にとって、二度目の大き過ぎる挫折体験でした。
日記の中では、父逝去の際に書かれた1960年5月5日、6日に転向に関して詳しく描かれています。また、破門については1955年8月7日に記された習作「小説と開業医の間」にその経緯や先生の複雑な心境が語り尽くされています。
二人の女性、母と妻
先生の両親への孝心はひとかたならぬものでした。長男であるが故に家業の農業を継ぐはずでした。しかし、津川少年の天賦を見抜いた中学校校長から強く進学を勧められ、ついには東京帝大入学を果し、医療の道へと歩み出します。それでも、若くして離別した二人が随分な時間を経て再会するかのように、先生は国政において厚生分野ではなく農水部門での地歩を固めて行きます。これは先生の幼少期の記憶と無縁ではないはずです。それほど農業に心血を注いだ父への敬意は深かったのです。
かたや、母への愛情も勝るとも劣らないものでした。日記に描かれた母の姿は老いと共に活発さが失われて行き、また嫁を不条理にも罵ることが多くなり、おそらくアルツハイマー型認知症だったのでしょう。でも、先生は母への寛容と関心を片時も欠かしませんでした。日記の行間から伺える母と息子の二人の様子はひたすら寡黙です。多忙の日々の中で時間を見付けては頻々と母を訪ねることで先生は満たされたのでしょう。時には、医師の視線から老母を冷静に見詰めています。時には、母と幼子のように枕を並べる夜もあったようです。現代日本では奇跡的とも言えるような幸福感が、母・イトと息子・武一の間に充ちていました。
一方、妻・ショウとは、男女の根源的なすれ違いをお互いに感じ取りながらも、実に豊かな関係を築き上げました。世の結婚生活の大概がそうであるように、夫・武一が妻・ショウから学んだことは決して少なくなかったと思われます。妻の見せる激情が、一見怒りの様相を借りながらも、実は怒りとしてしか表現することの出来ない妻の苦しさと期待であることを夫・武一は肌に突き刺さる感触と共に知るのです。
一方で、「俺は他人を愛することが出来る人間なのだろうか」という自分への問い掛けが日記には幾度も記されています。例えば、身近な人間との親密さに居心地の悪さを覚え、その裏返しとして遠い他人との関係に献身することで、結果的に社会貢献という形で成功している人物は枚挙に暇がありません。ですが、先生はそうではなく、葛藤を続けたのです。妻の容赦ない叱責を自分自身への問いとして捉え直し、何とか建設的な解決を見出そうと務めた先生の度量には感服するばかりです。大げさにはなりますが、全世界の夫を代表して先生は愛の困難性と克服への意志を広く告白したのです。これぞまさに先生の為し得た偉大なる社会貢献の一つとして数える上げるべきだと考えます。
いつまでも離れ難く、永遠の安らぎの源であった母との関係。その一方で、何度も衝突しながらも建設的であった妻との関係。この二つの関係を日記から感じとっていただきたいです。
私と公
 先生は暇さえあれば愛用の大学ノートを広げペンを走らせていました。往診の車中では膝の上に乗せたカバンを机替わりにしてペンを握り、自宅では妻の寝息が聞こる傍でノートを広げ、東京へ向かう寝台列車ではほの暗い照明を頼りに書き続けました。
先生は暇さえあれば愛用の大学ノートを広げペンを走らせていました。往診の車中では膝の上に乗せたカバンを机替わりにしてペンを握り、自宅では妻の寝息が聞こる傍でノートを広げ、東京へ向かう寝台列車ではほの暗い照明を頼りに書き続けました。
日記の内容と言えば、身辺雑記はもちろんのこと、折々の短歌、小説の構想、己の思想と行動についての反省と鼓舞など多岐に渡ります。とりわけ、先生が任に就いた健生病院院長、津軽保健生協組合理事長、そして衆議院議員のどれもが壮絶な公職でしたから、時にはその重圧に耐えかねて日記の中で「辞めてしまいたい」と弱気な心持ちを吐き出すこともありました。人前で口にするにはためらうようなグチや嘆き、弱音なども日記には度々記されています。幾重にも折りたたまれ、時には自家撞着を来たし、時には八方塞がりとなり、それでも前進することを止めなかった人間・津川武一の、複雑にして重層的な心理を垣間見る思いがします。
 では、心血を注いで先生がノートに文字を書き続けた本当の意図とは一体何だったのでしょうか。同時に、書き続けることで先生が実感し得た安らぎとはなんだったのでしょうか。十巻の厖大な記述を何度も読み返しましたが、結局、その中に「これぞまさしく本心から発せられた言葉」というものを見付けることが出来ませんでした。
では、心血を注いで先生がノートに文字を書き続けた本当の意図とは一体何だったのでしょうか。同時に、書き続けることで先生が実感し得た安らぎとはなんだったのでしょうか。十巻の厖大な記述を何度も読み返しましたが、結局、その中に「これぞまさしく本心から発せられた言葉」というものを見付けることが出来ませんでした。
その理由は幾つかありそうです。たとえば、永井荷風の『断腸亭日乗』のように、『武一日記』もいつかは人目に晒される時が来るであろうことを意識して書かれた可能性は多分にあるでしょう。また、日記というやや特殊な表現形式は、自分自身をさらけ出すことを本義とするのではなく、自分を突き放すための作業に他なりません。そこに描き込まれたものとはその瞬間の自己に過ぎず、過去とも未来ともなだらかに連なることの決してない、自由にして気紛れな、放埓であって無責任な、瞬時にして過ぎ去ってしまった自己でしかないのです。だからこそ、一番の核心は描かれないままであり、私たちの手の届かない遥か彼方に先生の内奥が秘されている、と私には思えてなりません。もっと言えば、私たちは先生の孤独な息遣いに触れてはならないのかもしれません。
そっと日記の一冊一冊を本棚に並べ、背表紙を眺め、時折、津川武一という人物の軌跡を思い返し、そして日本社会の歩みに思いを馳せる。今、私はそれで十分ではないかという気がしています。
さて、藤代健生病院誕生までの軌跡を辿るために、そして津川武一先生の壮年の日々に迫るために、いざ『武一日記』全十巻へと踏み出しましょう。
武一日記 = Index =
掲載:2019年2月28日
Copyright © 津軽保健生活協同組合 藤代健生病院 All Rights Reserved.