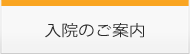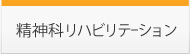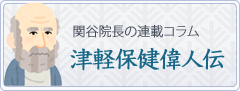津軽保健偉人伝 第1回「医師・岩淵謙一の魂魄」
医師・岩淵謙一の魂魄と 津軽保健生活協同組合の源流
津軽という風土、宿命的な苦悩、そして救済
藤代健生病院 関谷 修
岩木川と十三湖
津軽半島は独自の地形を成している。中でも、岩木川の一筋の流路は際立っている。
岩木川、それは白神、八甲田山系から無数の水脈を集めた急峻な流路が、平野に達するや一転し、呑気な、朴訥な様相を湛え、右に津軽山地、左に屏風山に挟まれながら屈曲を繰り返し、そして北上を続け、遂には十三湖に果つる。
十三湖が嘗ては現在の数倍もの大きさであったことは、考古学、地層学が膨大な調査、研究から雄弁に語るところである。時代の下ると共に、巨大な十三湖がいつしか水位を落とし、その規模を小さくするにつれて、岩木川という線状物やら、周辺の湖沼やら副水路をその名残として残し、現在の姿に至る。
歴史は反復を許すのであろうか。振幅に寛容なのであろうか。一見、穏やかな岩木川が、元の雄姿への回帰を自ら企図するかのごとくに、急激に秘めた野生を発揮し、牙を剥き、氾濫に至る。少なくとも、大正末期まで岩木川の治水は津軽の一大課題であり、一夜にして手塩の田が洪水で壊滅する悲劇を周辺の農民は幾度も味わってきた。
 太宰治の手になれば、その情景は次のように切り取られる。
太宰治の手になれば、その情景は次のように切り取られる。
「やがて、十三湖が冷え冷えと白く目前に展開する。浅い真珠貝に水を盛つたやうな、気品はあるがはかない感じの湖である。波一つない。船も浮んでゐない。ひつそりしてゐて、さうして、なかなかひろい。
人に捨てられた孤独の水たまりである。流れる雲も飛ぶ鳥の影も、この湖の面には写らぬといふやうな感じだ。十三湖を過ぎると、まもなく日本海の海岸に出る。」
「やつぱり、北津軽だ。深浦などの風景に較べて、どこやら荒い。人の肌の匂ひが無いのである。山の樹木も、いばらも、笹も、人間と全く無関係に生きてゐる。東海岸の竜飛などに較べると、ずつと優しいけれど、でも、この辺の草木も、やはり『風景』の一歩手前のもので、少しも旅人と会話をしない。」 『津軽』より
 ある種の残酷さを含ませた文章である。津軽の地を冷ややかに語り過ぎている。未開地ならまだしも、人を寄せ付けない峻厳な風景など、隅々までに人々が踏み込んだ津軽にあろうものか。まして、縄文の集落、十三湊の交易など、民の日常と殷賑と欲望が綯い交ぜになってきた土地柄である。そこに、人とも、生活とも折り合えない風景を見出す太宰は、すなわち社会と折り合いのつかぬ自らを見て取ったに他ならない。
ある種の残酷さを含ませた文章である。津軽の地を冷ややかに語り過ぎている。未開地ならまだしも、人を寄せ付けない峻厳な風景など、隅々までに人々が踏み込んだ津軽にあろうものか。まして、縄文の集落、十三湊の交易など、民の日常と殷賑と欲望が綯い交ぜになってきた土地柄である。そこに、人とも、生活とも折り合えない風景を見出す太宰は、すなわち社会と折り合いのつかぬ自らを見て取ったに他ならない。
太宰に近い感触を、半世紀の後、高村薫が語った。大阪生まれの稀代の文筆家は、津軽の風景に只ならぬ排他性を目撃して一驚した。
「レディ・ジョーカーを書き始める前の1993年に、たまたま青森を旅して七里長浜を見たんです。その風景に圧倒されて、いつか小説に書きたいと思っていました。『ぎゃーてーぎゃーてー』という般若心経と響きあう土地としてここを選んだのです。
気候の関係で、空もない海もない、ひたすら風が鳴っている。形あるものがない、見えないというのは、まさに般若心経の世界です。」
このたった一度の体験から、高村は『レディージョーカー』のプロットに青森を忍ばせ、さらに、『晴子情歌』『新リア王』『太陽を曳く馬』の長編三部作にまで昇華せしめた。
だが、我々、津軽に暮らす者にとって、太宰の自己愛的描写より、はたまた高村の透明度を極めた力技より、高木の朴訥にして陰鬱な感覚の方が遥かに生活実感に近いのではなかろうか。

高木恭造作『方言詩集』より
風景も人間もひっくるめて、ここまで楽観を捨て去る境地において初めて説得力が出てくる。救いのない程に、救いを期待しない心境である。これも間違いなく十三湖と岩木川に寄り添って暮らす民衆の息遣いである。
腰切り田
藩政期以降、岩木川下流に暮らす農民の日常には、他所とは比べようのない苦難の歴史が重く、深く刻まれることになる。弘前藩は少しでも石高を上げるべく耕作に不向きな痩せ地、湿地の開墾を農民に命じた。農民達に選択の余地などあろうはずもなく、嗚咽も呻吟も押し殺すようにして黙々と働き続けるよりなかった。明治に変わるや、今度は、地主が入会地にも年貢を課して来た。言い掛かりの論法に加えて腕力をちらつかせ、勤勉と禁欲を絵に描いたような農民としては、またしても俯くよりなかった。
だが、それ以上に彼らを苦しめたのが、二つの苦難であった。
第一の苦難は地形的条件であった。岩木川下流域の勾配は2万分の1と、川面は限りなく水平に近い。十三湖は日本海の荒波をまともに受ける汽水湖であり、湖面の水位によっては容易く川が逆流する。田圃に海水が流れ込み、初夏には伸び盛り稲穂の根元を襲い、秋には刈り取り干した稲を浚って行った。
また、極端な排水不良から、田は沼地と変わらず、中に入った農民の腰まで浸かれば「腰切り田」、胸まで浸かれば「乳切り田」と呼ばれた。水捌け用の側溝が完備される昭和の中頃までは、全身泥まみれとなる凄まじい光景が農作業の日常であり、「田植えの後は血の小便が出た」と言う。
 第二の苦難は、気象条件であった。水稲とは元来熱帯産の植物である。米を栽培し、米を主食とする小集団が、古代、九州からかなりの勢いで列島の日本海側を駆け上がり、ついには北限に至る。そこが津軽であった。
第二の苦難は、気象条件であった。水稲とは元来熱帯産の植物である。米を栽培し、米を主食とする小集団が、古代、九州からかなりの勢いで列島の日本海側を駆け上がり、ついには北限に至る。そこが津軽であった。
ところが江戸時代に入ると、小氷河期と呼ばれる長期的気候変動によって平均気温が約3度も低下し、稲の北限が数百キロメートルも南下してしまう。小説『津軽』の中で太宰が記す如く、江戸期、津軽の凶作は余りに多かった。5年と経たずして凶作が待ち受けていた。北津軽の農民はこれに耐え、命を賭けて闘い、ほとんど独力で共同体を維持し、あまつさえ石高を飛躍的に増大せしめた。これは語らぬ民の静かなる偉業ではなかろうか。
整然たる稲穂の揺れる夏の風景に往時を偲ぶよすがは、現在、聊かも見付けられない。果たして、これが幸福な風景と言い切れるであろうか。
青森が誇るべき名医
大正13年、日本医科専門学校を卒業して程ない青年医師、岩淵謙一は東京から車力村へと向かった。初代村医であった父が往診中に落馬し、他界したためである。
二代目村医として車力村に着任した岩淵は、日を追うごとに、農村の実態、農民の困窮した生活状況を知る。岩淵は「医療よりも先にまず栄養だ。生活の貧しさがこの人たちを病気にさせている」と痛切に実感する。
岩淵が農民に出す処方箋の裏には、「タマゴ」「鶏」と書かれていた。診療所から出る農民を待っていた妻は、着物の裾からそっと取り出し、渡していた。
求められれば厭わず愛馬を駆って遠方まで往診に出かけた岩淵は、行く先々で貧困の実像に直面する。それは、医師の子息であった幼少期には目に入らなかった車力村の光景であった。
薪すら用意できず、その代わりに焚かれたサルケが陰湿な煤を放ち、狭い農家の中に充満して、天候を問わずほの暗い。煤煙のために慢性化した眼疾から失明に至れば、イタコしか糊口を凌ぐ道はなかった。
土間を上がれば、大概、汚れきった布団に患者は寝かされていた。それは文字通りの万年床であり、婚礼の際に持参した布団が一度も洗われることないまま褐色に変色し、芬々たる匂いを発していた。
紡績工場の集団生活で結核に感染した娘が馘首され人目を避けるように部屋の片隅に蹲っていることも一再ならずあった。蒼白の面立ちに表情は失われ、家族からも疎んじられたまま自らの最期を待つしかない虚脱が余りにも痛々しかった。
 囲炉裏の鍋の中身を覗くと、具材は野良猫や野良犬だった。内臓はもちろんのこと表皮から、眼球から食べ尽くされ、最後は骨さえ煮込んで食べるのだと言う。子供らにその味と尋ねると、「うめぇ」と屈託の無い言葉が返って来た。
囲炉裏の鍋の中身を覗くと、具材は野良猫や野良犬だった。内臓はもちろんのこと表皮から、眼球から食べ尽くされ、最後は骨さえ煮込んで食べるのだと言う。子供らにその味と尋ねると、「うめぇ」と屈託の無い言葉が返って来た。
岩淵は、行く先々で貧困を目の当たりにして愕然となった。幾度も、幾度も。
小作組合結成
 青森の県民性として、感情表出に乏しいということはないはずだ。だが、不思議と、明治初期の不平士族らの不穏な動きも大事に至ることはなく、また、大正前期に全国を席巻した米騒動も本県に飛び火することはなかった。
青森の県民性として、感情表出に乏しいということはないはずだ。だが、不思議と、明治初期の不平士族らの不穏な動きも大事に至ることはなく、また、大正前期に全国を席巻した米騒動も本県に飛び火することはなかった。
しかし、大正末期、いよいよもって本県でも農民運動が本格化する。その口火を切ったのは車力村であり、指揮したのは岩淵自身であった。
診療所で孤軍奮闘する岩淵は己一人の力の限界を痛感し、個々の忍辱と尽力を超えた連帯の力へと希望の矛先を振り向けた。貧農家の経済的改善に向けて封建的土地制度に対抗するための争議を指導する体制を整えるべく同志を募り、密かに医院の裏の蔵で会合を重ねた。そして、大正13年秋、青森県初の農民組合である「車力小作組合」の結成に至る。大正14年4月には、小作料軽減について組合は地主と真っ向からの対決に臨み、鯵ヶ沢区裁判所での公判までに発展した。5月1日には県内初のメーデーを実施し、近隣農村からも含め参加者は数百名に及んだ。青森県下において、ついに連帯の力が表現された。
車力村議会選挙
大正14年5月、普通選挙法公布を受けて青森県下で市町村議会選挙が一斉に行われた。車力村村議会は定数12。すべての議席を旦那衆と呼ばれる有産階級が占めると思われていた。結成間もない車力小作組合からは、千載一遇の好機とばかり、中村専助が立候補し、地道な選挙活動を行った。一方、「車力の殿様」の異名を持つ大地主、鳴海周次郎は来る貴族院多額納税者議員選挙で、日商会頭、藤田謙一との一騎打ちの大一番が待ち受けているにも関わらず、拡大の勢い止まぬ組合に対する対策として自ら村議選に立候補した。加えて、息のかかった旦那衆に十分すぎるほどの利便を図り、水面下での工作に抜かりなかった。
ところがである、中村は30票を得て最下位ながらも当選し、片や、鳴海は29票と1票差で落選という大波乱が待っていた 。
鳴海は激怒すると同時に、農民たちの底知れぬ力を目の当たりにして、間髪を入れずに次の一手を打つことを決断。鳴海は当選した11人の村議を密かに集め、中心人物たる岩淵の追放を指示したのである。後日、村議会にて岩淵の村医取り消し処分が議題に上がり、村議の賛成多数により可決された。
地主らの支配層から追放されたとはいえ、岩淵に対する農民の思いは強いものであった。車力を追われ、八戸に向かう岩淵の姿をたくさんの農民たちが見送った。
無産者診療所
明治維新以降の経済成長と軌を同じくして、日本でも社会保障を無視しえない時代が到来する。急激に増大する工場労働者の健康を維持し、同時に壮健なる兵士の確保を万全にすべしという表向きの名目に加え、彼らの赤化を怖れた厚生省が中心となり公的医療保障制度の検討が始まり、大正11年には健康保険法、昭和13年には国民健康保険法の公布と、画期的な(はずの)制度の制定が続いた。
だが、その内実は、政府、市町村、各地医師会、資本家らの陣取り合戦であり、負担の押し付け合いであった。誰のための制度なのかという本質的な議論は深められることなく、駆け引きの結果出来上がった制度は欠陥欠落多くして、現場で汗水流す工場労働者や農漁民には恩恵の余りに乏しい内容に留まった。今、正に、彼らのための医療の場が必要とされた。
 昭和2年に岩淵は八戸に移住し、湊町にて岩淵医院を開設する。続いて、昭和5年には二十八日町で無産者診療所を開設するに至る。日中は自ら医院で診療、往診をこなした。午後6時からは無産者診療所に場所を移し、仕事を終えた工場労働者、農漁民の診療にあたった。しばしば、深夜まで彼らと向かい合った。
昭和2年に岩淵は八戸に移住し、湊町にて岩淵医院を開設する。続いて、昭和5年には二十八日町で無産者診療所を開設するに至る。日中は自ら医院で診療、往診をこなした。午後6時からは無産者診療所に場所を移し、仕事を終えた工場労働者、農漁民の診療にあたった。しばしば、深夜まで彼らと向かい合った。
同時に、無産者診療所は社会運動の拠点ともなった。志を同じくする者が集い、時代の要請と自らの志向の距離を計りつつ、『凶作に苦しむ農民には 政府米を無料で提供せよ』など切実なメッセージ、スローガンを積極的に発信した。
だが、岩淵が熱意を傾け、活躍し、広く支持されるほどに、公安当局は目を光らせ、特高警察の尾行、監視が強化された。折しも、大正デモクラシーの熱気と活力は過去へと押し遣られ、昭和の慢性的な不況と武力的抑圧へと転じる端境期にあった。
特高と拷問
昭和10年、晩秋の夜更に特高警察数名が岩淵の自宅に踏み込んできた。農民暴動を教唆した容疑にて取り調べを要すると居丈高に特高は説明した。晩酌していた岩淵は啖呵を切った。
「取り調べには応じる。だが、警察の車なんぞに乗れるか!」
岩淵は妻にタクシーを呼ばせ、その間、恬然と杯を傾けた。 到着した水上署では、机を挟んで刑事が詰問する。岩淵は怯むことなく自らの信念を訴える。
「多くの農民が病に苦しんでいる。その原因が貧困だ。貧乏から彼らを救うために、自分は医者として努力している。何が悪いのだ」
 あまりに全うなその言葉、容易には反駁しえない正義の論法を前に、刑事は言葉を詰まらせた。権力構造にしかと組み込まれた身上として、国家的大義を語る文法では民衆の生活感情は回収され得ないとは認め難い。時代的な葛藤を刑事は己の問いとして引き受けることはなく、逆上という否認の最も見苦しい形式でしか己の救いを見出せなかった。冷酷も激情も等しく容易く暴力へと置き換えられる。特高は岩淵に拷問を加えた。竹刀や鉄拳による殴打に始まり、冷水を浴びせかける、角材で大腿部を痛めつける。たちまち、大腿部は腫脹し皮下出血が広がる。拷問にも流行り廃りがあるのだろう、多喜二に加えた手法と同じであった。幾日にも渡る肉体的苦痛は熾烈を極めた。だが、岩淵の内面に湧き上がった屈辱と憤りはそれ以上であった。医師として、同時に人間としてのプライドを深く傷付けられたからであった。
あまりに全うなその言葉、容易には反駁しえない正義の論法を前に、刑事は言葉を詰まらせた。権力構造にしかと組み込まれた身上として、国家的大義を語る文法では民衆の生活感情は回収され得ないとは認め難い。時代的な葛藤を刑事は己の問いとして引き受けることはなく、逆上という否認の最も見苦しい形式でしか己の救いを見出せなかった。冷酷も激情も等しく容易く暴力へと置き換えられる。特高は岩淵に拷問を加えた。竹刀や鉄拳による殴打に始まり、冷水を浴びせかける、角材で大腿部を痛めつける。たちまち、大腿部は腫脹し皮下出血が広がる。拷問にも流行り廃りがあるのだろう、多喜二に加えた手法と同じであった。幾日にも渡る肉体的苦痛は熾烈を極めた。だが、岩淵の内面に湧き上がった屈辱と憤りはそれ以上であった。医師として、同時に人間としてのプライドを深く傷付けられたからであった。
一方、彼を慕う農漁民など貧民層らが手探りで署名活動を始めた。その輪が少しずつ広がり、支配階級である地主・船主、更には青森地裁検事の父など900名もの署名が集まり、分厚い釈放嘆願書が県の特高課に提出された。県は看過しえない事態であると判断し、岩淵を釈放する。昭和11年1月、岩淵は足を引き摺りながら帰宅する。家族と、そして少なからぬ人々が静かに彼を迎えた。
逐電の心得
張り切るばかりが能ではない。いよいよ以って我が身、我が精神の限界来ると断じた際、岩淵は逡巡なく十和田を目指した。「行くぞ」と一言岩淵が漏らすと、家族はそれとばかりに荷造りして蔦温泉へと急いだ。大町桂月との邂逅があったろうか。いずれにせよ、無床診療所だからこそ可能なる離れ業であった。こういう緩急で岩淵は自らの肉体の消耗を先送りし続けた。
そして、日本は太平洋戦争へと進む。
ポリオワクチン獲得運動
感染症との戦いは人類史の大分を占め、歴史上、多くのパンデミックが発生したことは言うを俟たない。そして、津軽もその例に漏れない。例えばインフルエンザ。江戸後期には「津軽風」と称する流行り病が見られたし、大正時代にはスペイン風邪が猛威を振るった。大正末期には、嗜眠性脳炎が本県に広がり、少なからぬ犠牲者を出している。
昭和30年代半ばに日本中を席巻したのがポリオであった。昭和34年7月には、八戸市内でポリオが集団発生する。まだ終戦後の色合いを濃く残し、インフラ整備は緒に着いたばかりで、上水と下水の区分は全くもって不分明。米を研ぐ横でイカや魚を洗い、汚れ物の洗濯も行い、極めて不衛生であったことが一因であった。だが、一地区の発生数としては異例の多さである。厚生省は、急場凌ぎとして1人分のワクチンを30人に分けて接種するよう指示を出した。しかし、八戸の母親らは、一晩で手足の麻痺を来すポリオの恐怖に慄き、思案した。ついに、彼女たちはワクチンを大量生産していたソ連からの輸入を求めて岩淵に嘆願した。岩淵は急遽、盟友津川武一を伴い上京しソ連大使館と交渉した結果、忽ち2万人分のワクチンが国内に到着した。
ところが厚生省は使用許可を渋り、大蔵省は高額の関税を課し、ワクチンは梱包されたまま羽田空港の税関で足止めを食らう。その背景には、米ソ冷戦の構図があり、またワクチン輸入業者や国内のワクチン製造会社の思惑が絡み合っていた。
 岩淵は厚生省、大蔵省、青森県庁を向こうに回し、一歩も引かぬ覚悟で交渉を続けた。その心中は、時間を空費することで感染患者が増加する危機を食い止めるため、「自分は医師免許を剥奪されてもいい」と未承認のソ連製ワクチンの接種に踏み切る覚悟を蔵していた。そして、幸いにも青森県議会、県医師会、弘前医大が次々と岩淵の活動を後押しした。その結果、厚生省は方針を変更し、ワクチンの全国一斉無料接種が開始される。
岩淵は厚生省、大蔵省、青森県庁を向こうに回し、一歩も引かぬ覚悟で交渉を続けた。その心中は、時間を空費することで感染患者が増加する危機を食い止めるため、「自分は医師免許を剥奪されてもいい」と未承認のソ連製ワクチンの接種に踏み切る覚悟を蔵していた。そして、幸いにも青森県議会、県医師会、弘前医大が次々と岩淵の活動を後押しした。その結果、厚生省は方針を変更し、ワクチンの全国一斉無料接種が開始される。
だが、岩淵は吉報を耳にすることなく自宅で急逝する。享年六十三。
津軽で医業に就く我々は、果たして己の正義のために、拷問に屈せぬ気概を持ち得るだろうか。果たして己の信じる道を捨てることなく放逐の憂き目を耐え忍ぶことができようか。
七人の侍
岩木川が源流から十三湖に流れ着くまで同様に、我々も容易には語り尽くせぬストーリーの奔流に呑み込まれつつ、立ち続けつつ、その責務を手離さないで来た。
黒澤明監督の長編大作『七人の侍』では、前半、農民たちが野武士の暴略から自らの土地を守る為に「安くて、強くて、物好き」な侍を当て度なく探し回るシーンが延々と続く。浪人という余剰の存在を許すポスト戦国時代の豊かな時世においてさえ、同時に農民の狡猾と侍の専横が表裏一体であり、それ自体が階級差を超えた忌まわしき人間性に他ならないという暗示が張り巡らされている。
 我々、藤代健生病院の一同は「安くて、強くて、物好き」な者でありたいと切に願う。己の力が役立つ限り、この地で、この場所で働くことを決意した者の結集である。銀幕の中では、生き残った侍は、七人のうち半分を割った。同じ運命を辿ろうがそれも亦良し、と我々は覚悟もしている。
我々、藤代健生病院の一同は「安くて、強くて、物好き」な者でありたいと切に願う。己の力が役立つ限り、この地で、この場所で働くことを決意した者の結集である。銀幕の中では、生き残った侍は、七人のうち半分を割った。同じ運命を辿ろうがそれも亦良し、と我々は覚悟もしている。
貧しい日本の、そのまた更に貧しさを上乗せしたような津軽。ここで医療を生業とする覚悟を決めた者が直面するものは、今も尚、病いと貧困の双方に喘ぐ民ではないのか。専横に与せず、さりとて狡猾に逃げることも潔しとはせず。ただただ、隘路を進まんとす。
了
掲載:2018年2月2日
Copyright © 津軽保健生活協同組合 藤代健生病院 All Rights Reserved.